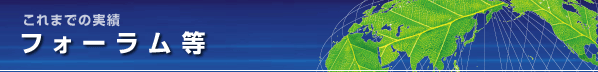| ■日 時 | : | 2023年11月2日(木曜日)13時40分〜16時50分 |
| ■場 所 | : | ホテル名古屋ガーデンパレス |
| ■参 加 者 | : | 当日参加者数 94名 |
| ■主 催 | : | 環境パートナーシップ・CLUB(EPOC) |
| ■後 援 | : | 経済産業省 中部経済産業局 環境省 中部地方環境事務所 一般社団法人中部経済連合会 名古屋商工会議所 一般社団法人中部産業連盟 一般財団法人省エネルギーセンター東海支部 |

プログラム
13時40分〜13時45分 【開会挨拶】
EPOC会長 小池 利和 ブラザー工業株式会社 取締役会長
EPOC会長 小池 利和 ブラザー工業株式会社 取締役会長

13時45分〜14時55分 【基調講演】
「水素の現状と今後の展開」
九州大学 副学長 水素エネルギー国際研究センター長 佐々木 一成 氏
「水素の現状と今後の展開」
九州大学 副学長 水素エネルギー国際研究センター長 佐々木 一成 氏
冒頭で過去・現在・将来のエネルギーのメガトレンドの流れや脱炭素イノベーションにおける水素の関わりを説明していただき、国内で再生可能エネルギーの利用を拡大する時や海外からコストの安い再生可能エネルギーを大量に輸入する時、排出されたCO2を回収して燃料化する時にも水素が不可欠となり、水素がカーボンニュートラル実現のカギとなることをわかりやすく教えていただきました。
燃料電池は水素を介して燃やさずに発電するため、従来の熱エネルギー変換から電気化学エネルギー変換にシフトし、しかも高効率発電となるため非常にポテンシャルが高いことを九州大学での実証実験の結果も交えて説明していただき、水素の普及にむけて水素価格の低下を実現するために乗用車や商用車への対応だけでなく発電や将来的には化学や製鉄といった産業分野もターゲットとしていることを学びました。
世界各国で水素に関わる投資が急拡大している中で、日本では2030年に最大300万トン/年の水素供給量、水素・アンモニアで電源構成の1%を目指すことや製造源や調達先を限定しないだけでなく発電、モビリティ、民生、産業などの用途も特に限定しないことを定めた国の「水素基本戦略」についても教えていただきました。
最後に九州大学の基盤研究や技術実証だけでなく社会実装や人材育成、国際連携への取組みを映像も交えて説明していただきましたが、「夢の燃料」実現に向けて日々チャレンジしている皆さんの映像が希望に満ち溢れていてとても印象に残りました。
質疑応答では参加した皆さんからの質問に対して、わかりやすく丁寧に回答していただきました。
燃料電池は水素を介して燃やさずに発電するため、従来の熱エネルギー変換から電気化学エネルギー変換にシフトし、しかも高効率発電となるため非常にポテンシャルが高いことを九州大学での実証実験の結果も交えて説明していただき、水素の普及にむけて水素価格の低下を実現するために乗用車や商用車への対応だけでなく発電や将来的には化学や製鉄といった産業分野もターゲットとしていることを学びました。
世界各国で水素に関わる投資が急拡大している中で、日本では2030年に最大300万トン/年の水素供給量、水素・アンモニアで電源構成の1%を目指すことや製造源や調達先を限定しないだけでなく発電、モビリティ、民生、産業などの用途も特に限定しないことを定めた国の「水素基本戦略」についても教えていただきました。
最後に九州大学の基盤研究や技術実証だけでなく社会実装や人材育成、国際連携への取組みを映像も交えて説明していただきましたが、「夢の燃料」実現に向けて日々チャレンジしている皆さんの映像が希望に満ち溢れていてとても印象に残りました。
質疑応答では参加した皆さんからの質問に対して、わかりやすく丁寧に回答していただきました。

14時55分〜15時05分 【休憩】
15時05分〜15時55分 【事例紹介 ①】
「カーボンニュートラルに向けた水素関連実証事業などの事例紹介」
株式会社大林組 執行役員 技術本部 副本部長 伊藤 剛 氏
「カーボンニュートラルに向けた水素関連実証事業などの事例紹介」
株式会社大林組 執行役員 技術本部 副本部長 伊藤 剛 氏
最初に大林組のカーボンニュートラルソリューションや水素社会に向けた状況の中での大林組の取り組みについてお話しいただきました。現在大林組では、再生可能エネルギー発電事業の推進として太陽光発電所28ヵ所、風力発電所2ヵ所、バイオマス発電所2ヵ所の稼働に関わり、フルラインナップ化に向けて地熱や小水力の開発にも取り組んでいます。水素の多様な製造方法や用途、将来に向けた水素の需要から判断してカーボンニュートラル実現には電化と水素化が必要となることを学びました。
次に大林組が手掛けている具体的な「水素関連実証事業」について教えていただきました。
水素は「つくる/はこぶ/つかう」の三拍子が必要となりますが、大林組では大分県の九重町の地熱発電から水素を「つくり」、九州各地に「はこび」、福島県の浪江町でも水素を「はこぶ」実験を行い、神戸のポートアイランドではNEDOの実証実験として発電に「つかう」検証を行っています。
具体的に神戸ポートアイランドでは水素Co-generation Systemから供給される電気と熱の最適配分に向けた統合型Energy Management Systemの改修・実証を実施し、地域における水素エネルギーの有効利用に向けた評価が行われていることを知りました。海外の事例としてはニュージーランドの水素をフィジーに運ぶ実証実験を行っていることや九重町の地熱水素を岡山県のサーキットに提供している事例についても学びました。
最後に水素普及に向けての課題や阻害要因、水素スタンドの規制緩和について教えていただき、質疑応答ではBCP用途としての水素活用メリットをわかりやすくご説明いただきました。
次に大林組が手掛けている具体的な「水素関連実証事業」について教えていただきました。
水素は「つくる/はこぶ/つかう」の三拍子が必要となりますが、大林組では大分県の九重町の地熱発電から水素を「つくり」、九州各地に「はこび」、福島県の浪江町でも水素を「はこぶ」実験を行い、神戸のポートアイランドではNEDOの実証実験として発電に「つかう」検証を行っています。
具体的に神戸ポートアイランドでは水素Co-generation Systemから供給される電気と熱の最適配分に向けた統合型Energy Management Systemの改修・実証を実施し、地域における水素エネルギーの有効利用に向けた評価が行われていることを知りました。海外の事例としてはニュージーランドの水素をフィジーに運ぶ実証実験を行っていることや九重町の地熱水素を岡山県のサーキットに提供している事例についても学びました。
最後に水素普及に向けての課題や阻害要因、水素スタンドの規制緩和について教えていただき、質疑応答ではBCP用途としての水素活用メリットをわかりやすくご説明いただきました。

15時55分〜16時45分 【事例紹介 ②】
「カーボンニュートラル社会の実現に向けたENEOSの取り組み−合成燃料の社会実装を目指して−」
ENEOS株式会社 中央技術研究所 首席研究員 菅野 秀昭 氏
「カーボンニュートラル社会の実現に向けたENEOSの取り組み−合成燃料の社会実装を目指して−」
ENEOS株式会社 中央技術研究所 首席研究員 菅野 秀昭 氏
はじめに日本の一次エネルギーにおける寄与率が約15%のENEOSグループではカーボンニュートラル指針として「エネルギートランジション」と「サーキュラーエコノミー」を推進していることやScope3がScope1,2の10倍になっていることを教えていただきました。
再生可能エネルギーが主力の社会では変動する電力と上手に付き合うことが必要となり、サプライチェーンはさらに弾力性が求められ、余剰電力を利用しやすい水素への投資が活性化されますが、日本では海外の再生可能エネルギーを活用することも必要であることを詳細に説明していただきました。
さらにカーボンニュートラルな燃料・エネルギーであるためには、安全性、エネルギーセキュリティ、経済性、環境性に加えてエネルギー供給会社が事業として成立することも要素となり、今後、電気や水素、バイオ燃料、合成燃料などのカーボンニュートラル燃料は適材適所で利用されることを学びました。
次に合成燃料の製造方法はFT製造法とMTG製造法の2種類あり、現在はジェット燃料や軽油の製造も可能なFT製造法が主力となっていること、合成燃料は人工的に製造されるので場所を選ばないこと、代替燃料がないジェット燃料を優先的に考えるケースがあることなどを教えていただきました。
最後にカーボンニュートラル燃料の供給に向けては、原料の調達や技術開発、法律・条約・ルールの整備などの課題を乗り越えながら、大きな目標に向かって様々な可能性を追いかけて挑戦し続けることが大切であることを学びました。
質疑応答ではいくつかの質問に対して、丁寧に回答していただきました。
再生可能エネルギーが主力の社会では変動する電力と上手に付き合うことが必要となり、サプライチェーンはさらに弾力性が求められ、余剰電力を利用しやすい水素への投資が活性化されますが、日本では海外の再生可能エネルギーを活用することも必要であることを詳細に説明していただきました。
さらにカーボンニュートラルな燃料・エネルギーであるためには、安全性、エネルギーセキュリティ、経済性、環境性に加えてエネルギー供給会社が事業として成立することも要素となり、今後、電気や水素、バイオ燃料、合成燃料などのカーボンニュートラル燃料は適材適所で利用されることを学びました。
次に合成燃料の製造方法はFT製造法とMTG製造法の2種類あり、現在はジェット燃料や軽油の製造も可能なFT製造法が主力となっていること、合成燃料は人工的に製造されるので場所を選ばないこと、代替燃料がないジェット燃料を優先的に考えるケースがあることなどを教えていただきました。
最後にカーボンニュートラル燃料の供給に向けては、原料の調達や技術開発、法律・条約・ルールの整備などの課題を乗り越えながら、大きな目標に向かって様々な可能性を追いかけて挑戦し続けることが大切であることを学びました。
質疑応答ではいくつかの質問に対して、丁寧に回答していただきました。

フォーラムを終えて
2023年の東京の猛暑日が観測史上初めて20日を超え、温暖化対策が喫緊の課題となっている中で、太陽光発電や風力発電と同様に水素・アンモニア発電による電力の脱炭素化に加え、天然ガスなどの非電力の脱炭素化にも活用でき、燃やしてもCO2を発生しない「水素」が「カーボンニュートラル実現のカギ」と言われている理由を今回のフォーラムを通じて理解していただくことができたと思います。
水素に関連する技術開発及び再生可能エネルギーなど原料のコストダウンや安定的な供給体制、法律やルールの整備など取組むべき課題は数多くありますが、エネルギー供給会社を中心に様々な実証実験を各地域で行い、日々チャレンジを繰り返すことで産業革命以来のエネルギーシフトを実現させなければ、持続可能な社会が見えてこないこともフォーラムを通じて理解していただけたと思います。
EPOCでは2030年ビジョンにも掲げている持続可能な経済社会の実現に向けて、今後も会員や地域の皆さまのお役に立てるよう、勉強会や交流会等を開催して参りますので引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。
最後に、ご講演いただきました講師の方々には、この場をお借りしてお礼申し上げます。
水素に関連する技術開発及び再生可能エネルギーなど原料のコストダウンや安定的な供給体制、法律やルールの整備など取組むべき課題は数多くありますが、エネルギー供給会社を中心に様々な実証実験を各地域で行い、日々チャレンジを繰り返すことで産業革命以来のエネルギーシフトを実現させなければ、持続可能な社会が見えてこないこともフォーラムを通じて理解していただけたと思います。
EPOCでは2030年ビジョンにも掲げている持続可能な経済社会の実現に向けて、今後も会員や地域の皆さまのお役に立てるよう、勉強会や交流会等を開催して参りますので引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。
最後に、ご講演いただきました講師の方々には、この場をお借りしてお礼申し上げます。